除法
20 ÷ 4 = 5. 20 個のりんごを 4 つに等分配したとき、それぞれのグループにはりんごが 5 個ある。
除法は ÷ や /, % といった記号を用いて表される。除算する 2 つの数のうち一方の項を被除数 (英: dividend) と呼び、他方を除数 (英: divisor) と呼ぶ。有理数の除法について、その演算結果は被除数と除数の比を与え、分数を用いて表すことができる。このとき被除数は分子 (英: numerator)、除数は分母 (英: denominator) に対応する。被除数と除数は、被除数の右側に除数を置いて以下のように表現される。
- 被除数 ÷ 除数
- 商 × 除数 + 剰余 = 被除数
剰余は余りとも呼ばれ、除算によって「割り切れない」部分を表す。剰余が 0 である場合、「被除数は除数を割り切れる」と表現され、このとき商と除数の積は被除数に等しい。剰余を具体的に決定する方法にはいくつかあるが、自然数の除法については、剰余は除数より小さくなるように取られる。たとえば、13 を 4 で割った余りは 1、商は 3 となる。これらの商および剰余を求める最も原始的な方法は、引けるだけ引き算を行うことである。つまり、13 を 4 で割る例では、13 から 4 を 1 回ずつ引いていき(13 − 4 = 9, 9 − 4 = 5, 5 − 4 = 1 < 4)、引かれる数が 4 より小さくなるまで引き算を行ったら、その結果を剰余、引き算した回数を商とする。これは自然数の乗法を足し算によって行うことと逆の関係にある。
剰余を与える演算に % などの記号を用いる場合がある。
- 剰余 = 被除数 % 除数
除数が 0 である場合、除数と商の積は必ず 0 になるため商を一意に定めることができない。従ってそのような数 0 を除数とする除法の商は未定義となる(ゼロ除算を参照)。
- 商 × 除数 = 被除数
という関係が除数が 0 の場合を除いて常に成り立つ。この関係は次のようにも表すことができる。
- 被除数 ÷ 除数 = 商
実数などにおける定義から離れると、除法は乗法を持つ代数的構造について「乗法の逆元を掛けること」として一般化することができる。一般の乗法は交換法則が必ずしも成り立たないため、除法も左右 2 通り考えられる。
目次
[非表示]
- 1整数の除法
- 2有理数の除法
- 3実数の除法
- 4複素数の除法
- 50で割ること
- 6ユークリッド除法と除算アルゴリズム
- 7等分除と包含除
- 8伝承
- 9脚注
- 10参考文献
- 11関連文献
- 12関連項目
- 13外部リンク
整数の除法[編集]
| 演算の結果 | |
|---|---|
| 加法 (+) | |
| |
| 減法 (−) | |
| 被減数 − 減数 = 差 | |
| 乗法 (×) | |
| |
| 除法 (÷) | |
| |
| 剰余算 (mod) | |
| |
| 冪 | |
| 底冪指数 = 冪 | |
| 冪根 (√) | |
| 次数√被開方数 = 冪根 | |
| 対数 (log) | |
| log底(真数) = 対数 | |
整数 m と n に対して、
- m = qn
を満たす整数 q が唯一つ定まるとき、m ÷ n = q によって除算を定める。m は被除数(ひじょすう、英: dividend)あるいは実(じつ)と呼ばれ、n は除数(じょすう、英: divisor)あるいは法(ほう、英: modulus)と呼ばれる。また q は m を n で割った商(しょう、英: quotient)と呼ばれる。商 q は他に「m の n を法とする商」「法 n に関する商 (英: quotient modulo n)」 などとも言う。 またこのとき、m は n で整除(せいじょ)される、割り切れる(わりきれる、英: divisible)あるいは n は m を整除する、割り切るなどと表現される。このことはしばしば記号的に n | m と書き表される。 除数 n が 0 である場合を考えると、除数 0 と任意の整数 q の積は 0 となり、被除数 m が 0 なら任意の整数 q が方程式を満たすため、商は一意に定まらない。同様に被除数 m が 0 以外の場合にはどのような整数 q も方程式を満たさないため、商は定まらない。
整数の範囲では上述のような整数 q が定まる保証はなく、たとえば被除数 m が 7 の場合を考えると除数 n が 1, 7, −1, −7 のいずれかでない限り商 q は整数の範囲で定まらない。整数の範囲で商が必ず定まるようにするには、剰余(じょうよ、英: remainder, residue)を導入して除法を拡張する必要がある。つまり、方程式
- m = qn + r
を満たすような q, r をそれぞれ商と剰余として与える。このような方程式を満たす整数 q, r は複数存在するが(たとえばある q, r に対して q − 1 と n + r の組は同様に上記の方程式を満たす)、剰余 r の取り得る値に制限を与えることで一意に商 q と剰余 r の組を定めることができる。よく用いられる方法は剰余 r を除数 n より絶対値が小さな非負の数と定めることである。このような除法はユークリッド除法と呼ばれる。
- m = qn + r かつ 0 ≤ r < |n|
これは、感覚的には被除数から除数を引けるだけ引いた残りを剰余と定めているということである。こうして定められる剰余はしばしば「m の n を法とする剰余」「m の法 n に関する剰余 (英: residue modulo "n") 」などと言い表される。 剰余 r が 0 でないことはしばしば「m は n で割り切れない」と表現され、記号的に n ł m と表される。 ユークリッド除法による計算例は以下の通りである。以下では除数を 4, −4, 被除数を 22, −22 としている。
- 0 ≤ r < |n|
- 22 = 5 × 4 + 2:商 5, 剰余 2
- 22 = (−5) × (−4) + 2:商 −5, 剰余 2
- −22 = (−6) × 4 + 2:商 −6, 剰余 2
- −22 = 6 × (−4) + 2:商 6, 剰余 2
絶対的最小剰余[編集]
他の剰余に対する制限の方法として、剰余の絶対値が最小となるように商を定める方法がある。この方法では、
- −|n|2 < r ≤ |n|2
あるいは
- −|n|2 ≤ r < |n|2
の範囲に剰余 r が含まれる。この場合、ユークリッド除法と異なり r は負の値を取り得る。このようにして定められる剰余を絶対的最小剰余 (least absolute remainder, absolutely least residue, minimal residue) と呼ぶ。 絶対的最小剰余を用いる場合の計算例は以下の通りである。以下では除数を 4, −4, 被除数を 22, −22 としている。
- −|n|2 < r ≤ |n|2
- 22 = 5 × 4 + 2:商 5, 剰余 2
- 22 = (−5) × (−4) + 2:商 −5, 剰余 2
- −22 = (−6) × 4 + 2:商 −6, 剰余 2
- −22 = 6 × (−4) + 2:商 6, 剰余 2
- −|n|2 ≤ r < |n|2
- 22 = 6 × 4 − 2:商 6, 剰余 −2
- 22 = (−6) × (−4) − 2:商 −6, 剰余 −2
- −22 = (−5) × 4 − 2:商 −5, 剰余 −2
- −22 = 5 × (−4) − 2:商 5, 剰余 −2
いずれの方法であっても、除数 n が 0 の場合、剰余 r は 0 でなければならず、被除数 m がどのような数であっても商 q を一意に定めることはできない。 絶対的最小剰余とユークリッド除法によって定められる最小非負剰余、あるいは別の方法のいずれを用いるかは自由であり、与えられる剰余がそのいずれかであるかは予め決められた規約に従う。この規約は、計算する対象や計算機の機種、あるいはプログラミング言語により、まちまちである。簡単な分析とサーベイが "Division and Modulus for Computer Scientists" という文献にまとめられている[1]。
有理数の除法[編集]
整数の除法では考えている数(自然数もしくは整数)の範囲内で商を取り直し剰余を定義することにより、除法をその数の範囲全体で定義することができることを述べた。しかしよく知られているように、数の範囲を有理数まで拡張し、商のとり方に有理数を許すことにより、剰余の概念は取り除かれ、有理数の全体で四則演算が自由に行えるようになる。
任意の被除数 a と 0 でない除数が b について、それらの除算は有理数 c を唯一つ与える。
- {\displaystyle a\div b=c.}
この有理数 c は
- {\displaystyle c\times b=b\times c=a}
を満たす。また、除法は除数の逆数の乗算に置き換えることができる。
- {\displaystyle a\div b=a\times {\frac {1}{b}}.}
従って除算および乗算の順序は入れ替えることができる。
- {\displaystyle {\begin{aligned}(a\div b)\times c&=\left(a\times {\frac {1}{b}}\right)\times c=(a\times c)\times {\frac {1}{b}}=(a\times c)\div b,\\(a\div b)\div c&=\left(a\times {\frac {1}{b}}\right)\times {\frac {1}{c}}=\left(a\times {\frac {1}{c}}\right)\times {\frac {1}{b}}=(a\div c)\div b.\end{aligned}}}
また、2 つの除算は乗法を用いてまとめることができる。
- {\displaystyle (a\div b)\div c=a\div (b\times c).}
しかし、除数と被除数を入れ替えることはできない。
- {\displaystyle a\div b\neq b\div a,}
- {\displaystyle (a\div b)\div c\neq a\div (b\div c).}
2つ目の例のように括弧の位置を変えると計算結果が変わってしまうので、
- {\displaystyle a\div b\div c}
と書かれた場合には特別な解釈を与える必要がある。一般的には左側の演算が優先され、下に示す右辺の意味に解釈される。
- {\displaystyle a\div b\div c=(a\div b)\div c.}
有理数の除法について、除数を被除数に対して分配することができる。
- {\displaystyle (a+b)\div c=a\div c+b\div c}
ただし被除数を除数に対して分配することはできない。
- {\displaystyle a\div (b+c)\neq a\div b+a\div c}
有理数の除算の結果は分数を用いて表すことができる。
- {\displaystyle a\div b={\frac {a}{b}}.}
ある有理数に対応する分数の表し方は無数に存在する。たとえば 0 でない有理数 c を用いて、
- {\displaystyle a\div b={\frac {ac}{bc}}={\frac {\frac {a}{c}}{\frac {b}{c}}}}
と表してもよい。 また有理数は分母と分子がともに整数である分数を用いて表すことができる。2 つの有理数 a, b をそれぞれ整数 p, q, r, s を用いて分数表記する。
- {\displaystyle a={\frac {p}{q}},~b={\frac {r}{s}}}
すると、それらの除算は次のように計算することができる。
- {\displaystyle {\frac {p}{q}}\div {\frac {r}{s}}={\frac {p}{q}}\times {\frac {s}{r}}={\frac {p\times s}{q\times r}}={\frac {ps}{qr}}.}
この表示から明らかなように有理数を有理数で割った商はまた有理数である。あるいは次のように計算してもよい。
- {\displaystyle {\frac {p}{q}}\div {\frac {r}{s}}={\frac {p\div r}{q\div s}}={\frac {\frac {p}{r}}{\frac {q}{s}}}.}
実数の除法[編集]
実数は有理数の極限として表され、それによって有理数の演算から実数の演算が矛盾なく定義される。すなわち、任意の実数 x, y (y ≠ 0) に対し xn → x, yn → y (n → ∞) を満たす有理数の列{xn}n ∈ N, {yn}n ∈ N(例えば、x, y の小数表示を第 n 桁までで打ち切ったものを xn, yn とするような数列)が与えられたとき
- {\displaystyle x/y:=\lim _{n\to \infty }x_{n}/y_{n}}
と定めると、この値は極限値が x, y である限りにおいて数列のとり方によらずに一定の値をとる。これを実数の商として定めるのである。
複素数の除法[編集]
実数の除法を用いれば複素数の除法が、被除数が 0 の場合を除いた任意の 2 つの複素数について定義できる。 2 つの複素数 z, w について、w の共役複素数 w を用いれば、複素数の除法 z/w は次のように計算できる(ただし除数 w は 0 でないとする)。
- {\displaystyle {\frac {z}{w}}={\frac {z}{w}}{\frac {\overline {w}}{\overline {w}}}={\frac {z{\overline {w}}}{\left|w\right|^{2}}}.}
また、複素数 z, w の実部と虚部を 4 つの実数 Re z, Im z, Re w, Im w を用いて z = Re z + i Im z, w = Re w + i Im w と表せば、複素数の除法 z/w は次のように表せる。
- {\displaystyle {\frac {z}{w}}={\frac {\operatorname {Re} z+i\operatorname {Im} z}{\operatorname {Re} w+i\operatorname {Im} w}}={\frac {\operatorname {Re} z\operatorname {Re} w+\operatorname {Im} z\operatorname {Im} w}{(\operatorname {Re} w)^{2}+(\operatorname {Im} w)^{2}}}+i\,{\frac {\operatorname {Re} z\operatorname {Im} w-\operatorname {Im} z\operatorname {Re} w}{(\operatorname {Re} w)^{2}+(\operatorname {Im} w)^{2}}}.}
極形式では
- {\displaystyle {\frac {z}{w}}={\frac {|z|e^{i\arg z}}{|w|e^{i\arg w}}}={\frac {|z|}{|w|}}e^{i(\arg z-\arg w)}}
と書ける。やはり |w| = 0 つまり w = 0 のところでは定義できない。
0で割ること[編集]
- 詳細は「ゼロ除算」を参照
代数的には、除法は乗法の逆の演算として定義される。つまり a を b で割るという除法は
- {\displaystyle a\div b=x\iff a=b\times x}
を満たす唯一つの x を与える演算でなければならない。ここで、唯一つというのは簡約律
- {\displaystyle bx=by\Rightarrow x=y}
が成立するということを意味する。この簡約律が成立しないということは、bx = by という条件だけからは x = y という情報を得たことにはならないということであり、そのような条件下で強いて除法を定義したとしても益が無いのである。
実数の乗法において、簡約が不能な一つの特徴的な例として b = 0 である場合、つまり「0 で割る」という操作を挙げることができる。実際、b = 0 であるとき a = bx によって除法 a ÷ b を定めようとすると、もちろん a = 0 である場合に限られるが、いかなる x, y についても 0x = 0 = 0y が成立してしまって x の値は定まらない。無論、a ≠ 0 ならば a = 0x なる x は存在せず a ÷ b は定義不能である。つまり、実数の持つ代数的な構造と 0 による除算は両立しない。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%B3%95
とても興味深く読みました:ゼロ除算の発見4周年超えました:
再生核研究所声明 416(2018.2.20): ゼロ除算をやってどういう意味が有りますか。何か意味が有りますか。何になるのですか - 回答
ゼロ除算とは例えば、100割るゼロを考えることです。普通に考えると、それは考えられない(不可能)となるのですが、それが分かることが まず第1歩です。この意味が分かるまでは、 次には進めませんので、興味があれば、 次で解説されている最初の方を参照してください:
ゼロ除算の研究状況は、数学基礎学力研究会 サイトで解説が続けられています: http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku/
できない(不可能である)と言われれば、何とかできるようにしたくなるのは相当に人間的な素性です。いろいろな冒険者や挑戦者を想い出します。ゼロ除算も子供の頃からできるようにしたいと考えた愛すべき人が結構多く世界にいたり、その問題に人生の大部分を費やして来ている物理学者や計算機科学者たちもいます。現在、ゼロ除算に強い興味を抱いて交流しているのは我々以外でも海外で 大体20名くらいです。ある歴史家の分析によれば、ゼロ除算の物理的な意味を論じ、ゼロ除算は不可能であると最初に述べたのはアリストテレス(BC 384-322) だということです。
また、アインシュタインの人生最大の懸案の問題だったと言われています。実際、物理学には、形式的にゼロ分のが 出て来る公式が沢山有って、分母がゼロの場合が 問題になるからです。いま華やかな宇宙論などでブラックホールや宇宙誕生などと関係があるとされ、ゼロ除算の歴史は 神秘的です。
ところが、ゼロを数学的に厳密に扱い、算術の法則を発見したインドのBrahmagupta (598 -668 ?) は 何と1300年も前に、0/0 はゼロであると定義していたというのです。それ以来1300年を超えてそれは間違いであるとされて来ました。1/0 等は無限大だろうと人は考えて来ました。関数 y=1/x を考えて、 原点の近くで考えれば、限りなく正の無限や負の無限に発散するので人は当然そのように考えるでしょう。天才たちもみんなそうだと考えて、現代に至っています。
ところが偶然4年前に 驚嘆すべき事実を発見しました。 関数 y=1/x の原点の値をゼロとすべきだという結果です。聞いただけで顔色を変える数学者は多く、数年経っても理解できない人は多いのですが、素人がそれは美しい、分かったと喜ぶ人も多いです。算術の創始者Brahmaguptaの考え、結果も 実は 適当であった。正しかったとなります。― 正しいことを間違っているとして来た世界史は 恥ずかしいのではないでしょうか。
この結果、無限の彼方(無限遠点)、無限が 実はゼロ(ゼロで表される)だったとなり、ユークリッド、アリストテレス以来の我々の空間の考えを変える必要が出て来ました。案内の上記サイトで詳しく解説されていますが、私たちの世界観や初等数学全般に大きな影響を与えます。どんどん全く新しい結果、現象が発見されますので、何といっても驚嘆します。 内容レベルが高校生にも十分分かることも驚きです。例えば、y軸の勾配がゼロで、tan (\pi/2) =0 だという驚きの結果です。数学というと人は難しくて分からないだろうと思うのが普通ではないでしょうか。そこで、面白く堪らなく楽しい研究になります。 現在、簡単な図を沢山入れてみんなで見て楽しんで頂けるような本を出版したいと計画を進めています。
内容は上記サイトで、相当素人向きに丁寧に述べているので、興味のある方は解説の最初の方を参考にして下さい。
以 上


























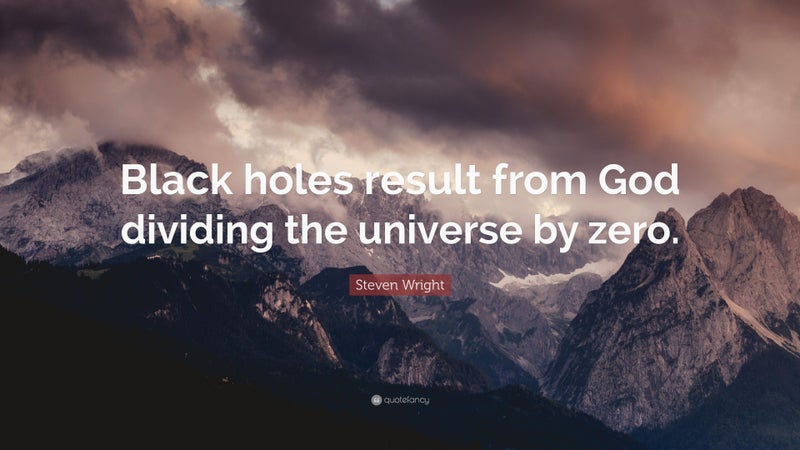



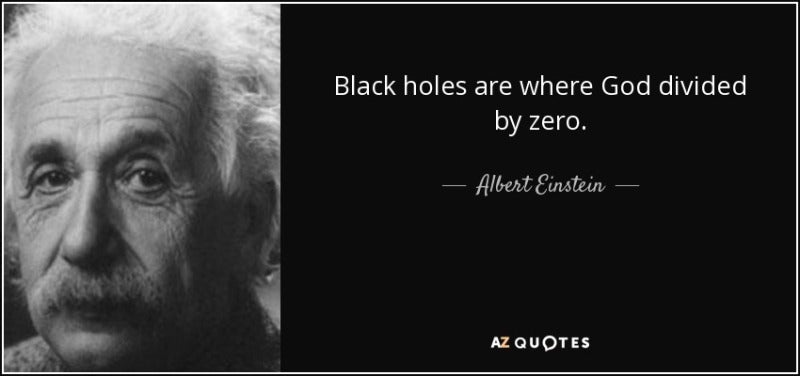











0 件のコメント:
コメントを投稿